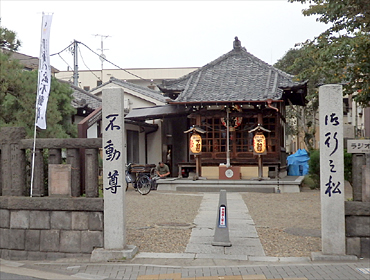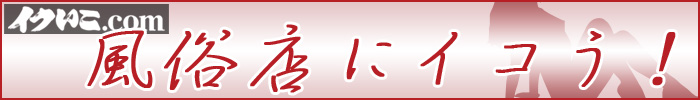 HOME
首都圏・業種別
首都圏・沿線別
イクいこ.com
HOME
首都圏・業種別
首都圏・沿線別
イクいこ.com
| 鶯 谷 へ よ う こ そ ! ◆女性を取材(サンケイスポーツ紙上でも掲載)したお店の紹介です |
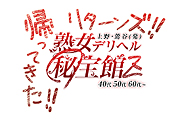 |
『熟女デリヘル秘宝館Z』
・業種 / 40〜60代の人妻熟女専門店 |
 |
『SCENE(シーン)』
・業種 / 熟女専門デリヘル |
 |
『ローズガーデン』
・業種 / 40代〜50代リアル人妻系デリヘル |
 |
『プチマドンナ』
・業種 / 熟女専門デリヘル |
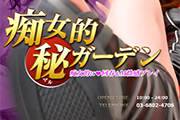 |
『痴女的マル秘ガーデン』
・業種 / 濃厚回春M性感 |
 |
『東京マダム』
・業種 / 人妻美熟女デリヘル |
| ◆以下の店は女性の取材記事はこれからになりますが、 サンケイスポーツ新聞上で広告を掲載しているお店です |
 |
『ミセス・グランデ』
・業種 / 人妻・お姉さん系デリヘル |
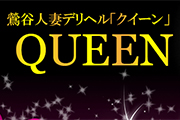 |
『クィーン』
・業種 / 淑女熟女デリヘル |
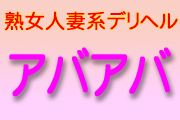 |
『アバアバ』
・業種 / 熟女人妻系デリヘル |
鶯谷駅の左方向、言問通りを渡った方のホテル街が途切れる辺りに、ひっそりとした
感じの板塀に囲まれた古い建物『子規庵』(夏目漱石とか幸田露伴とかも訪れた
文人達の集いの場ともなっていた俳人・正岡子規の住居。
現在の建物は、戦災で焼けてしまって弟子達が再建したもの)があるけど、上記の俳句はその子規の呼んだ句。
(ちなみにその斜め向かいに『書道博物館』がある)
鶯谷駅の住所は、根岸だ。
だから、駅名も「根岸」或いは霊園が広がる崖上側の住所「上野桜木町」と付けられたのならすんなり納得がいくんだけど、
でも「鶯谷」。
それはね、駅周辺にいっぱいラブホが出来て、夜な夜な女の忍びなく声、嬌声が聞こえてくるから、
その切なそうな鳴き声をウグイスに例えて、駅名も鶯谷になったんだよ...なんて話は昔、
まだ童貞だった少年君達が得意げによく囁きあっていた戯言だ。
ただ、なぜ「鶯谷」になったのかは、よくわかってはいない。
鶯は、ひばり、鶴とともに根岸の三鳥といわれていて往時の自然の中の鳥であったことは間違いない。
江戸時代、寛永寺(駅の崖上の霊園は寛永寺の所有。
徳川慶喜が一時籠もったのもここだし上野戦争で負けるまで幕府側、彰義隊側の地でもあった。
谷中霊園も元は寛永寺の土地だったし、当時はもっと広範囲に土地を所有していた)の住職がウグイスを放ち、
それでウグイスの名所になったからとも言われている。
また、元禄の頃、京から江戸に来た宮様が「江戸の鶯は、なまってごじゃるの〜」ってことで、
京からもっと鳴き声の素晴らしい鶯を運んでこさせて放った。
それ以来、鶯の名所となり、鶯谷の地名がついたとも。
ちなみに「ウグイスの鳴き合わせ」なんて文章を残してくれた人もいる。
「私らが来た時分は、向こうの人道が根岸の本通りで、そこへウグイスをもっていって、
帳面もって鳴くのを聞いて一等、二等を決めるんです。
角の足立屋さんだとか大塚さんだとかあるあそこの一角に「鶯春亭」っていう本名島田っていう料理屋があって、
そこがたまり場でね。ウグイスの会を明治43年の大水の時まではよくやってました。
その後もありましたが大震災まで続いたかな。
藪ウグイスをもって来て育てるんですが、捕るのは米俵を一本抜いてね、
もちを塗ってそれで竹薮においとくと、すぐひっかかった」
(岡本平次郎さんという人の記『古老がつづる台東区の明治・大正・昭和』より)
いずれにしても、鶯谷ってのは駅名だけで、地名があったわけではない。 ついでに言っちゃえば、「鶯谷駅」は、山手線の駅ではない。 戸籍上は東北本線の駅みたいだ。 明治42年(1909年)に新橋とか上野とか田端とかが電化されて、「鶯谷駅」はその3年後に開業されたそうだ。 昭和45年(1970年)に建てられた南口の駅舎は今も健在。 山手線29駅の中で、もっとも乗降者が少ない駅(2017年時点で1日25,000人弱)らしい。
◆鶯谷にラブホがこんなに多く出来た訳は
渋谷の丸山町とか新宿の歌舞伎町とかのラブホ街を通ると、いかにも『ファッションホテル』
『ラブホテル』街ってな感じがするんだけど、鶯谷の場合は年配者なんかには、
どうも「連れ込み旅館」街ってな印象を強く抱いてしまうらしい。
建物の規模が、前記の街などより概ね小さいってのもある。
それに建物と建物の間の道が、鶯谷の場合は車が通り抜けられるか抜けられないぐらいの狭い道がほとんどってこともある
(それも真っ直ぐな道ではなく、江戸時代からの道筋のままくねっていたり)。
階段は急だし、汚らしいし、ここだけはイヤだってなデリヘル嬢もいれば、
壁が薄くて隣の嬌声が聞こえてくるのが何ともイイっていうお客がいたりする。
ほんとに古い旅館はもう1軒しか残っていないんだけどね。
それと鶯谷っていうと、他地域と比べて熟女系の店が圧倒的に多いせいもあるのかも知れない。
そんな鶯谷のラブホ街は、例えば渋谷の円山町のラブホ街が岐阜のダム建設で沈んだ村の人達によって
形造られて行ったみたいな経緯があるわけではなく、ある意味で自然発生的に出来上がっていったらしい。
最初は普通の旅館として、他所から来た人達が建てたわけではなく、もともとその地でインク屋をやっていた人とか
下駄屋をやっていた人とかが旅館に建て替えて始めたみたいなんだ。
それも旅行客を泊めるのではなく、仕事で移動している人を泊めるというのが主流だった。
上野や浅草と違って、鶯谷なら大きな土地を持っていなくても小旅館としてやっていける。
あそこの旅館、人が入ってるねぇ、じゃあウチも...ってんで自宅を改築して旅館やってみるかってな調子でね。
そして旅館が増え、連れ込みとして発展していったのは近くにかつての赤坂の『みかど』に匹敵するような、
いろいろなショーなどもやっていた規模の大きなキャバレーが2軒あったというのが大きかったみたいだ。
そこのホステス達が店が引けたあと泊まっていったり、客と同伴で入ったりしていた。
それと根岸にはいろんな文豪や歌舞伎役者の別邸があったり、歩いていけるほどのところの距離
(人力車もよく使われていたみたいだけど)には、金杉通りと柳通りが交差している辺りその先に
「花柳界(三業地)」があって、今は影形も残ってないけど、
かなりの数の芸者さんもいたみたいだから必然的にそういう使われ方をされるようになっていったというわけだ。
繁華街ではないけど繁華街が近く、利用客が多かったために地元民が転業してホテル街になっていったというのが
鶯谷ホテル街の特徴みたいだ。
ホテルを改装したり、リニューアルする度にホテル名も変えていく。
ここでは老舗という暖簾は役にたたず、絶えず名前も新しく変えていかないと成り立たないとも誰か言っていた。
余談だけど、鶯谷には風営法が改正されて無許可の店舗が一掃され、新しく店舗を立ち上げるのも不可能になってから、
特にデリヘル等の業者の利用が増えた。
しかし宿泊料金が比較的安いということもあって、週末には普通のカップルが遠征してきてラブホを利用したりしている。
おかげで週末、安いホテルから満室になってしまうということもあって、ちょっとなぁ...って嘆いていた某店のオーナーもいたよ。
◆北口左方向、ラブホが途切れる辺りに「子規庵」や「書道博物館」
鶯谷駅北口を出ると、その辺り一帯は待ち合わせ型のデリヘル嬢の到着を今か今かと待つ男達の溜まり場...なんて。
改札出て線路沿いに沿って飲み屋・食べ物屋が6〜7軒が入った古い建物。
それより先一帯はほとんどがラブホテル。
その反対側一帯もラブホテル。
駅前から真っ直ぐ方向の車両の通れる幅さがある道路の左右両側にコンビニやファーストフード店、
チェーン店のカフェ(ここは風俗嬢はじめ、風俗関係者の利用が多い)、交番などがある他は、
だいたいがラブホって思っても間違いない街だ。
ラブホ街に突っ込んでいくようなくねった路地を行けば、先ほど紹介した古い旅館の建物の前を通ることになる。
その先、その辺りから車道が上下2本に分かれて走るのが「言問通り」なんだけど、そこの信号を潜って真っ直ぐ行けば、
その辺り一帯もラブホテル街。
時々、どう見てもラブホ利用者とは趣が違うオジサン・オバサンとかのグループを見かけることがあるけど、
そういう人達が目指しているのはだいたいがラブホが途切れたところに位置する「子規庵」だったり
「書道博物館」(洋画家で書家でもあった中村不折が収集した書道関係の博物館)
だったりする(林家三平の記念館もこっち方向の先)。
◆豆富料理屋『笹乃雪』 北口を出て広い道路を真っ直ぐ進むと、すぐ車の行き来の激しい「言問通り」にぶつかる。 さらに信号を越えて駅から続く通り(尾久橋通り)を真っ直ぐ進むと、すぐ右の通り沿いに小学校があって、 その校舎の壁には『御行の松』(後で説明)の大きなレリーフが認められる。 そしてそのちょうど向い側になる左へ折れる道との角の建物が、江戸時代より続く300年以上の歴史のある豆富料理屋 『笹乃雪』(「豆腐」ではなく「豆富」としたのは9代目とのこと)だ。 かつては吉原で遊んだ帰りに、寄って食事をしてったりした人が絶えなかったともいう老舗だよ。
◆元三島神社と入谷七福神
北口駅前の道を歩き出して右側は、2〜3軒コンビニなどの店をやり過ごしてすぐのところに路地みたいな道がある。
曲がりくねった道なんだけど、ここもラブホ地帯ではあるんだけど、途中すぐ目に入ってくるのが石塀に囲まれた神社だ。
ここが「元三島神社」。
下谷七福神の一つで、寿老神を祀っている。
この神社は蒙古襲来の弘安の役の際、河野通有が伊予国大三島の大山神社に必勝祈願し、その後、
武蔵国豊島郡に分霊を勧請して弘安4年(1281年)に創建したのが始まりという。
※ついでに他の下谷七福神を記しておくと、英信寺(大黒天)、入谷鬼子母神(福禄寿)、法昌寺(毘沙門天)、
朝日寺(弁財天)、飛不動(恵比寿)、寿永寺(布袋尊)となる。
「恐れ入谷の鬼子母神」と俚諺にうたわれて有名になったのは真源寺。
毎年7月の6〜8日にこの寺の境内から言問通りの歩道いっぱい使って行われる「朝顔市」は、いつも人出でいっぱい。
下谷の朝顔が有名になったのは明治の初め頃で、明治末期まで活況を呈するが、
入谷が市街地化されるに従い植木屋の廃業が相次いで下火となり、昭和23年に「朝顔市」として復活する。
◆鶯谷駅南口
改札口を出ると、すぐ目の前がタクシー乗り場。
あまりスペースのない広場で、待ちタクシーが入りきれなくて道路側に並んでいることも。
ここは、吉原に行く人の専用タクシー駐車場だ...なんて言っちゃいたくなるほど、
ここからタクシーに乗ってく人は吉原に遊びにイク人、それと当然ながら吉原のソープ嬢が多い。
広場の右方向に目を向けると、角のところに古い蕎麦屋の木造建物があったんだけど、最近取り壊されて更地になって
道路の向こう側の中学校の建物が目に入るようになった。
中学校の前の、やや坂になってる道を登っていって左方向へ舵を切ってさらに歩んで行くと、やがて国立博物館とかに辿り着く。
上野駅から歩いてくるより、鶯谷駅から歩いていった方が早いんだけど、
こっちから博物館や上野の公園を目指していく人はほとんどいないようだ。
上野に行く方向と反対側、鶯谷駅のホームから見える崖上は、そこから日暮里方向に向って寛永寺霊園がずっと続いている。
慶喜はじめ徳川家の将軍も何人か眠っていて歴史的な著名人の墓も多い霊園だけど、
寛永寺の建物自体に行くには鶯谷駅北口から行った方が早い日暮里寄り側にある。
なお、この寛永寺は上野の山から続く上野戦争の舞台となって、彰義隊が抵抗した場所として有名だけど、
元はと言えば寛永2年(1625年)に慈眼大師天海大僧正が、平安の昔(9世紀)、
桓武天皇の帰依を受けた天台宗の宗祖・伝教大師最澄上人が開いた比叡山延暦寺が京都御所の鬼門に位置し、
朝廷の安穏を祈る鎮護国家の道場であったことにならって、伝教大師・最澄上人が、
徳川幕府の安泰と万民の平安を祈願するため江戸城の鬼門(東北)にあたる上野の台地に建立した寺とのことだ。
◆鶯谷公園から言問通りを右へ
北口を出て、山手線等の線路を跨ぐ高架橋を左に行って階段を降り、そのすぐ左側一帯はラブホ地帯になるのだけど、
角の立ち飲み屋を曲がってラブホ街に入っていく入り口近くに小さな公園がある。
もう何年前になるのか、かつてヘイトスピーチで世を騒がせた某会デモの出発地点になっていたりしたことがあったところだ。
その時の、特に拡声器を通して響く女の人のアジる怒鳴り声は本当に迫力があった。
韓デリも、景気悪くてグァムとかオーストラリアとかに逃げてったなんて話が伝わってきたりしたのも、もう少し前のことになる。
そして今でこそ数は少なくなっているけど、韓国籍の人がこれを耳にした時は確かに恐かっただろうなって思ったくらい凄かったよ。
高架橋を降りて左に曲がらず、真っ直ぐ進めば、すぐに「言問通り」に出る。
左に行けば北口近辺を通ってやがて道は左にカーブして行って根津方面に向うんだけど、逆に右方向に行けば、
そこからはほぼ真っ直ぐ道になっていて、先は浅草寺の裏の方を通ってやがて隅田川の「言問橋」へと抜けることになるのだ。
南口からその言問通りに出て、右方向へ行くとすぐに車の流れが多い昭和通りと交差するんだけど、
曲がらずにまっすぐ行けばやがて地下鉄の入谷駅に。
先に紹介した入谷鬼子母神の真源寺は、それより手前の右歩道側にある。
◆金杉通り、旧三業地地帯、御行の松
昭和通りまで行かなくて、その手前の左に折れる道が「金杉通り」。
昔は都電が路面を走っていた通りで、吉原へ行くタクシーはこの金杉通りにいったん入って、それからすぐ右に曲がる。
そこからは吉原へは一本道。
どこまでも真っ直ぐ、国際通りの越えて道が突き当たるところまで行って左に曲がるとそこから先が吉原だ。
最近でこそあまり古い建物はなくなってしまったけど、この金杉通り付近は震災でも空襲でも
あまり被害を受けずに焼け残った建物もあるという珍しい一帯で、古い建物を偲んでよく人々が訊ねてきたりの街だった。
詳しくは触れないが、もともとこの金杉通りは寛永年間(1624〜1644年)に出来たといわれる奥州裏街道の名残で、
けっこう商店なんかで賑わった時もあったのだ。
三業地があったのも、この金杉通りを少し行くと「柳通り(昔は安楽寺横丁と言っていた)」という道にぶつかるんだけど、
その柳通りの左の方一帯だったらしい。
ということで、金杉通りを散歩することがあったら、柳通りを左へ曲がってもらいたい。
三業地だった痕跡とかはもうないけど、途中の道沿いに林家三平の
大きな文字が入った袢纏などがショーウインドウに飾ってある呉服屋があったり、ぽつんぽつんとだけど
老舗っぽい店があったりする地域だ。
そしてそのもう少し先を右に曲がったところには「御行の松」が祀られている
「御行の松公園」に出くわす。
「御行の松」は、かつて『江戸名所図会』や広重の錦絵にかかれたりしていた高さ13,6m、幹回り4m余りあった、
浅草や吉原からも見えたという松だ。
名前の由来は、松の下で輪王寺宮(江戸時代の寛永寺の門主)が修業したからだということで大正15年に都の天然記念物に指定されたけど、
昭和3年に枯れ死してしまった。
現在は3代目の松が育てられているらしいけど、樹齢300年の根株が残っていてそれなら見ることが出来る。
ちなみに、その御行の松まで来る道は「御行の松通り」ってなっているよ。
先に書いた、北口からすぐの「笹乃雪」のところで、向かいに小学校があって「御行の松」の
大きなレリーフがあるといったのは、この「御行の松」のことだ。
根岸小学校だけど、発祥の地としては今の位置ではなく、この御行の松通りの途中に「発祥の地」としての
記念碑が残っているを見られたりする。
この辺りまで来ると、江戸や昭和の昔日が何となく忍ばれ、鶯谷ってラブホの街だったことなど頭の中から抜けちゃったりする。
根岸、ホントいろんな顔を見せる面白い街だ。
でも鶯谷っていったら、やっぱりラブホの街、女の嬌声がウグイスのように響き渡る街だよなぁ。
「寮の根岸」「紅梅の根岸」「鶯の根岸」「初音の里」「呉竹の里」でも、もちろんいいけどね。
まぁ、どっちにしろオトナが楽しめる街には違いないよ。
------
※参考にさせてもらった文献
・酒井不二雄『東京路上細見3 - 上野・御徒町・谷中・入谷・根岸』(平凡社 / 1988年刊)
・陣内秀信、板倉文雄他『相模選書:東京の町を読む - 下谷・根岸の歴史的生活環境』(相模書房 / 昭和56年刊)
・竹内誠『東京の地名由来辞典』(株フォレスト / 2006年刊)
・日本アートセンター『東京・文化財の旅』(毎日新聞社 / 1999年刊)
・台東区立下町風俗資料館『古老がつづる台東区の明治・大正・昭和』(台東区教育委員会 / 昭和56年刊)
・村上信彦『大正・根岸の空』(青蛙房 / 昭和52年刊)
・人文社観光と旅編集部『東京都 - 郷土資料事典、観光と旅13』(人文社 / 平成元年刊)
・沢寿次『山手線物語』(日本交通公社出版事業局 / 昭和46年刊)
・高橋美江『新版 絵地図師・美江さんの東京下町散歩』(新宿書房 / 2013年刊)
・本橋信宏『東京最後の異界 鶯谷』(宝島社、2013年刊)
・金益見『性愛空間の文化史 - 連れ込み宿からラブホまで』(ミネルヴァ書房 / 2012年刊)
・松本典久『JR山手線の謎 - 2020』(実業の日本社・じっぴコンパクト新書 / 2018年刊)
・朝日新聞社会部『東京地名考(上)』(朝日新聞社・文庫版 / 昭和61年刊)